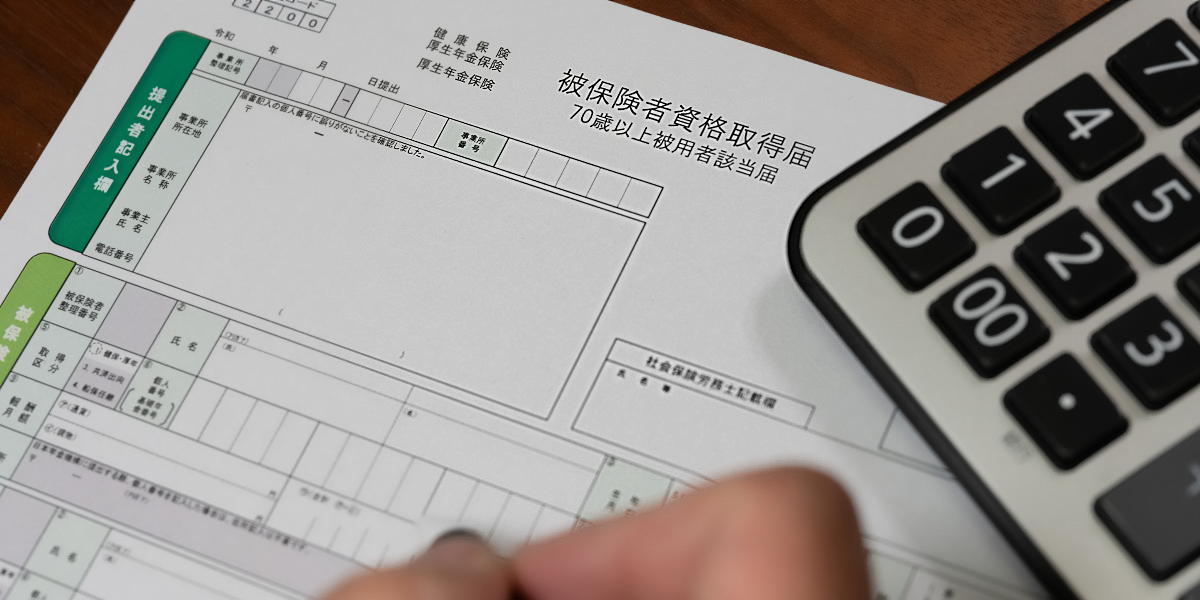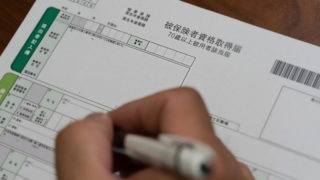在職中は職場で用意してもらえた健康保険証も退職をしたら自分で用意しなければなりません。
今回は、いくつか選択肢がある退職後に加入できる健康保険のなかで「健康保険任意継続」と「国民健康保険」の2つをくらべてみました。
退職後の健康保険(国民皆保険)
国民健康保険法により日本国民である以上なんらかの健康保険制度に加入しなければなりません。
国民皆保険 こくみんかいほけん
すべての国民をなんらかの医療保険に加入させる制度。医療保険の加入者が保険料を出し合い,病気やけがの場合に安心して医療が受けられるようにする相互扶助の精神に基づく。日本では 1961年に国民健康保険法(昭和33年法律192号)が改正され,国民皆保険体制が確立された。
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典(抜粋)
会社を退職した場合、健康保険は次のいずれかから選ぶようになります。
- それまでの健康保険に引き続き加入する。(任意継続)
- 住所地の国民健康保険に加入する。
- 家族が加入する健康保険の被扶養者になる。
- 再就職先が決まっている場合、新しい会社の健康保険に加入する。
今回は、表題のとおり⒈の健康保険任意継続と⒉の国民健康保険に絞ってくらべてみました。
健康保険任意継続
健康保険任意継続は、退職後もそれまでと同じ健康保険の被保険者資格を継続できる制度です。
条件は退職前の被保険者期間が2カ月以上、期間は最長2年間までとなっています。
任意継続の手続き
この制度を利用するためには、退職日翌日から20日以内に、加入していた健康保険によって、健康保険組合事務所、あるいは協会けんぽの支部で本人が手続きを行わなければなりません。
必要書類は「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」ですが、場合によって被扶養者の収入を証明する書類が必要になることがあります。
任意継続の保険料
保険料は在籍時の会社による半額負担がなくなり全額自己負担となるので通常それまでに比べ高くなります。
単純計算すると2倍ですが、任意継続では保険料算出基準額に上限があるので退職前の給与額によってはそうならないようです。
任意継続の主な注意点
- 手続き期間(退職日翌日から20日以内)を過ぎると、基本的に手続きできない。
- 保険料の滞納があると即資格喪失になる。
- 一度手続きすると2年間変更できない。
国民健康保険

国民健康保険は、市区町村が保険者となる健康保険です。
保険料(国保税)の算出方法は自治体によって異なり、会社都合で退職する場合などに受けられる軽減措置制度があります。
国民健康保険の加入手続き
国民健康保険に加入するためには、原則として退職日翌日から14日以内に住所地の市区町村役場担当窓口にて手続きを行います。
必要書類は、離職票や健康保険の資格喪失証明書等の退職日の確認できるものと、マイナンバーカード、運転免許証など本人を証明する書類になります。
申請書は窓口に用意されていますし、自治体によってはマイナンバーカードを省略できるケースもあるようです。
国民健康保険の保険料
保険料は前年の収入等を根拠に各市区町村ごとの基準で計算されます。
また、扶養者の概念がないので世帯全員の保険料を納付する必要があります。
国民健康保険の主な注意点
- 手続きは退職日翌日から14日
- 家族全員分の保険料納付が必要
健康保険任意継続と国民健康保険の比較
健康保険任意継続と国民健康保険のポイントを比較できるよう簡単な表にまとめてみました。
| 任意継続 | 国民健康保険 | |
| 手続き期日 | 退職後20日以内(厳守) | 退職後14日以内 |
| 手続き場所 | 健康保険組合健康保険協会 (加入保険による) |
市区町村役場の国保担当窓口 |
| 加入の条件 | 退職日以前に社会保険に継続して2ヶ月以上加入していた人 | 他の健康保険に属していない人 |
| 加入期間 | 最大2年間 | 条件を満たしている期間 |
| 必要書類 | 資格取得申出書 | 健康保険の資格喪失証明書 |
| 脱退の条件 | 加入してから2年が経過したとき 就職などで、新たに社会保険に加入することになったとき 後期高齢医療の資格を取得したとき 保険料を期日までに納付しなかったとき |
他の健康保険に加入したとき |
結局どちらを選ぶべき?
ここまでで手続き方法や加入期間等すこしづつ違いがあることが分かりましたが、検討の際最も重要になるのが保険料ではないでしょうか。
退職の理由によっては保険料支払いの優遇制度が使える可能性があり、その制度を使えるか否かによって保険料に違いが出るようです。
退職理由が会社都合退職の場合
国民健康保険の軽減制度が適応になる可能性があります。
適応すれば、保険料算出の基準となる前年給与所得を100分の30にして計算されるので、国民健康保険のほうが割安になる確率が高くなります。
退職理由が自己都合退職の場合
国民健康保険の軽減制度がありません。
国民健康保険は基本的に前年の収入で保険料が算出されます。
また、扶養の概念がないので扶養者全員の保険料を支払わなければならず保険料が高くなる傾向があるようです。
それに対して、任意継続では算出基準となる退職時給与の上限が設定されていたり特定の要件を満たせば扶養家族と認められたりするため、退職時に高い給与を受け取っていた場合や扶養家族が多い場合は保険料負担を低く抑えることができるかもしれません。
さいごに
健康保険の保険料は、「退職時の給与額」「扶養する家族の数」「住居地」「国民健康保険の軽減制度が適応になるか」など複数の要素で決まるため、どちらを選べばよいかは人それぞれのようです。
「健康保険任意継続」と「国民健康保険加入」の二択で迷っているならば、どちらも保障に変わりはないので少しでも有利な制度を選べるよう保険料を試算してもらうとよいでしょう。